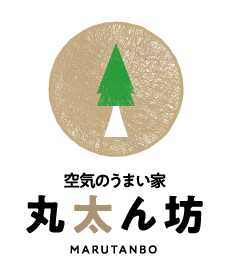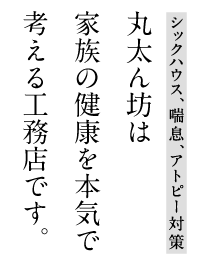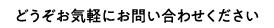新緑がまぶしく、さわやかな風が心地よい5月ですね(^_^)。
4月からの新しい環境にはもう慣れましたか?
なにか気に病むようなことがあれば一歩外に出て、草木のにおいを感じてみたり、どこか懐かしい風の音を聞いて、胸の奥深くまで深呼吸をしてみてください。きっと前向きな気持になれるのではないでしょうか。
とても良い季節ですが、あっという間に過ぎてしまうので、一日一日大切に過ごしていきたいものです!
さてこの時期になると、あちこちで田んぼに水が張られはじめ、風に揺れる水面がキラキラと光り出します。私は田舎育ちだったので、その様子を見るたびに「あぁ、田植えの季節が来たなぁ」と感じます。
最近は「お米が足りない」といったニュースも耳にしますが、スーパーで袋に詰められて並んでいるお米が、どれだけたくさんの手間と時間をかけて作られているか、考えたことはありますか?
お米作りは、実は冬から始まっています。農家さんは寒いうちから田んぼの整備を進め、春になるとまず「種もみ」を水に浸け、発芽させます。これが「浸種(しんしゅ)」という作業。
発芽した種もみを土にまいて、「育苗(いくびょう)」と呼ばれる苗づくりが始まります。ハウスの中で育てることもあり、温度や水の管理にはとても気を使うそうです。
一方で、田んぼの準備も進みます。田を耕し、水を張って、土を細かく砕いてならす「代かき(しろかき)」という作業を行います。これを丁寧にすることで、苗がまっすぐ育ちやすくなるのです。
そしていよいよ田植え本番。育てた苗を一本一本、田んぼに植えていきます。今は田植え機があるとはいえ、端の部分は手作業だったり、足元がぬかるんでいたりして、体力も集中力も必要な大変な作業です。
でも、ここで終わりではありません。
田植えのあとも、夏には雑草との戦いや、田んぼの水量の調整、病害虫の防除など、気の抜けない日々が続きます。自然の力を借りながら、でも自然に負けないように向き合いながら、農家さんたちは稲を育てていくのです。
私は以前、子どもと一緒に田植え体験に参加したことがあります。泥に足を取られながら一歩一歩、苗を植えていく作業は、思った以上に重労働。でもその分、秋にそのお米を炊いたときの喜びといったら!
「この一粒が、あのときの苗なんだね」と、子どももニコニコしていました。毎日のごはんには、農家さんの知恵と努力、そして自然の恵みがぎゅっと詰まっています。「いただきます」のひと言に、もっと心を込めたくなりますよね。
この春、もし近くで田植えの風景を見かけたら、ちょっと立ち止まって見てみてください。何気ない風景の中に、たくさんのドラマが隠れているかもしれませんよ。