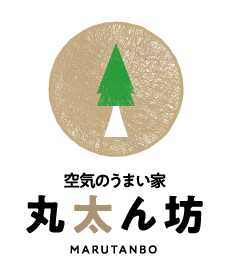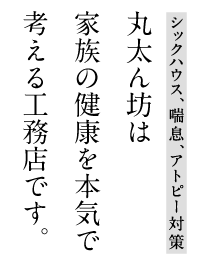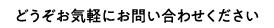5月の風物詩といえば、やはり「鯉のぼり」。青空に悠々と泳ぐ姿は、日本の春を彩る風景のひとつです。
でも、そもそもなぜ「鯉」が選ばれたのでしょうか? その理由には、古くからの伝説や人々の願いが込められています。
鯉のぼりの由来をたどると、中国の「登竜門伝説」に行き着きます。黄河の上流にある急流「龍門」という滝を、数多くの魚たちが登ろうと挑戦します。
しかし、その流れは激しく、ほとんどの魚は途中で力尽きてしまいます。そんな中、鯉だけが滝を登りきり、やがて龍へと変身して天に昇ったという物語です。
この伝説から「鯉は出世魚」「困難を乗り越えて成功する象徴」とされ、鯉のぼりにも「どんな困難にも負けずに立派に成長してほしい」という願いが込められるようになりました。
武家文化から庶民の祝いへ
江戸時代、武家の間では男の子が生まれると「のぼり旗」や「槍旗」を掲げて祝う風習がありました。これがやがて町人文化にも広がり、庶民はのぼり旗の代わりに「鯉のぼり」を飾るようになります。
当初は黒い「真鯉」一匹でしたが、時代が進むにつれ家族を象徴する鯉たちが加わりました。赤い「緋鯉」は母親、青い「子鯉」は子どもを表し、家族の無事と繁栄を祈る意味合いも持つようになります。
たくましさの象徴としての鯉
また、鯉は生命力が非常に強い魚としても知られています。
きれいな川はもちろん、泥水のような厳しい環境でもたくましく生き抜く鯉の姿は、「逆境に負けない強さ」の象徴です。そんなたくましさが、子どもたちの成長に重ねられ、鯉のぼりに託されたのです。
現代では、素材やデザインも多様化し、カラフルで個性豊かな鯉のぼりが空を舞います。
大きさもさまざまで、家庭用の小さなものから、地域で飾る巨大な鯉のぼりまでありますが、そこに込められた願いは昔も今も変わりません。
「元気に育ってほしい」「夢に向かって羽ばたいてほしい」という親心が、鯉のぼりには静かに息づいているのです。