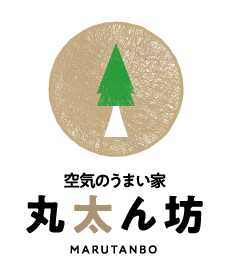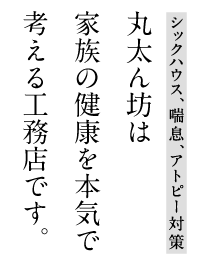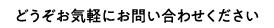9月になると、昼間はまだ汗ばむほどの暑さでも、朝や夜の空気がふっと涼しく感じられる日が増えてきます。
ふと空を見上げれば、入道雲が姿を消し、やわらかなうろこ雲やすじ雲が広がりはじめ、空の色も夏の濃い青から少しやさしい色合いに変わっていきます。
庭先や街路樹の葉も、まだ青々としていながらも、ほんのり色づく準備を始めています。こうした小さな変化が、秋の入り口を知らせてくれます。
昔の人は、この時期を「二百二十日(にひゃくはつか)」と呼びました。立春から数えて220日目、ちょうど9月上旬にあたります。
台風が多く訪れる時期で、稲の収穫を目前に控えた農家にとっては、もっとも気を抜けない“勝負どころ”でした。今もこの言葉は農業暦などに残り、日本の季節感を表す言葉のひとつになっています。
秋の楽しみといえば、「中秋の名月」も欠かせません。旧暦の8月15日にあたるこの日、一年のうちでも特に月が美しいとされ、お月見団子やススキを供えて月を愛でる風習があります。
ただし、天文学上の満月と必ずしも重なるわけではなく、1日前後ずれる年もあるのが面白いところです。月の光は、涼やかさとともに、どこか心を落ち着かせてくれます。
また、9月1日は「防災の日」。1923年の関東大震災にちなんで制定され、台風や地震など災害への備えを見直す日とされています。季節の変わり目は天候も不安定になりやすいので、この機会に備蓄や避難経路を確認しておくと安心です。
そしてお彼岸の頃、田んぼのあぜ道や川沿いで鮮やかに咲くのが「彼岸花」。花が咲いてから葉が出るという、ちょっと不思議な植物で、その真紅の花は秋の訪れを告げるサインのようです。
今年の9月は、空や風、花や月といった自然の移ろいを意識してみませんか。暑さの名残と秋の気配、その両方を味わえるのは、この時期ならではの楽しみです。