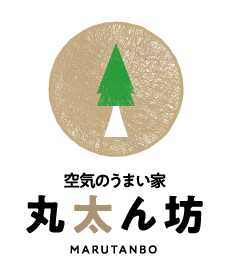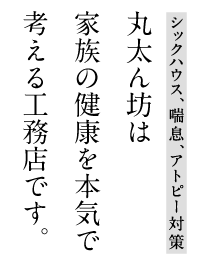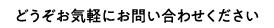皆さん、いかがお過ごしですか?
私は夏の間、あまりの暑さにシャワーばかりで済ませていましたが、最近はようやく入浴するようになりました。
湯船にたっぷりとお湯をはり、お気に入りの入浴剤を入れて入るお風呂はいいですよね。疲れがとれるというか、こわばっていた全身の筋肉が弛緩していく感じがなんとも言えません。日本人に生まれて良かったぁと思う瞬間です。
ところで、今でこそどのご家庭にもお風呂があるのは当たり前ですが、それっていつ頃からかご存知ですか?
そもそも「入浴」の概念が日本に伝わってきたのは6世紀頃と言われています。仏教とともに中国から伝わってきたそうです。
仏教の「斎戒沐浴(さいかいもくよく)」、つまり修行として身を清めるという考え方です。なので、寺院は一般の人々に向けて「施浴(せよく)」を行ったのですね。
ただ、まだこの頃は体の汚れを落とすことが目的ではありませんでした。でも施浴を通じて人々は入浴のもたらす清潔さと病気治癒の効果を徐々に知っていくことになります。
その後、慶長時代の末期、1610年頃でしょうか。「据え風呂」というものが普及します。
この頃がどんな時代だったかというと1600年は関ケ原の戦い、1615年は大坂夏の陣で豊臣氏が滅亡した頃です。
よく温泉に行くと信玄の隠れ湯とか、秀吉なら有馬温泉に度々通い湯治をしたなどとお聞きになったことがあると思います。有馬温泉には秀吉が湯治施設として湯山御殿を建設したとも言われています。
つまり、温泉地に行かないとなかなかお湯に浸かって入浴することができなかったのでしょう。それが据え風呂が普及したことにより、庶民にも家での入浴の習慣が広まっていきました。
その後、薪でお湯を沸かす「鉄砲風呂」が生まれます。これは木桶の浴槽内部に鉄製の筒を設置し、その筒の下で薪を燃やして沸かす方式でした。主に江戸を中心に広まったそうです。
関西では鉄製の平釜を使ってお湯を沸かす「五右衛門風呂」が主流となったとのこと。五右衛門風呂は鉄製の風呂釜に直火で加熱してお湯を沸かす方式で、釜の底は高温になるので火傷しないように踏み板を沈めて入るのです。
実は私が小さい頃、親戚の家のお風呂が五右衛門風呂でした。今思えば貴重な体験をしたのだなと思います(笑)。
そのお風呂も進化して、今ではミストサウナがついていたり、首筋から肩のあたりにお湯が出る肩湯があったりと、様々な機能が充実しています。
またユニットバスではなく、お風呂をオーダーできる会社も増えています。
岐阜にはとても美しい檜風呂を作っておられる檜創建さんという会社もありますし、広島には鋳物ホーローの浴槽を得意とされている大和重工さんがありますし、京都にはオーダーバス専門のスピリチュアルモードさんという会社があります。
これらの会社のお風呂は有名ホテルにも数多く採用されているので、最高にリラックスできるお風呂に拘りたい方は、色々と検討してみてくださいね。
それでは秋の夜長、お風呂をゆ〜っくりとお楽しみください\(^o^)/